はじめに
就職したけど、私には合わないな、思っていた職場と違う...
急に倒産したんですけど!!
違うことがしたくなった、仕事を辞めて勉強もしたい...
出産して仕事を休まないといけなくなった!
という時に助けになるのが、雇用保険です。
今回は、そんな失業したときなどに対象となる雇用保険について詳しくみていきましょう。
↓退職代行お願いしたい方はこちらから↓

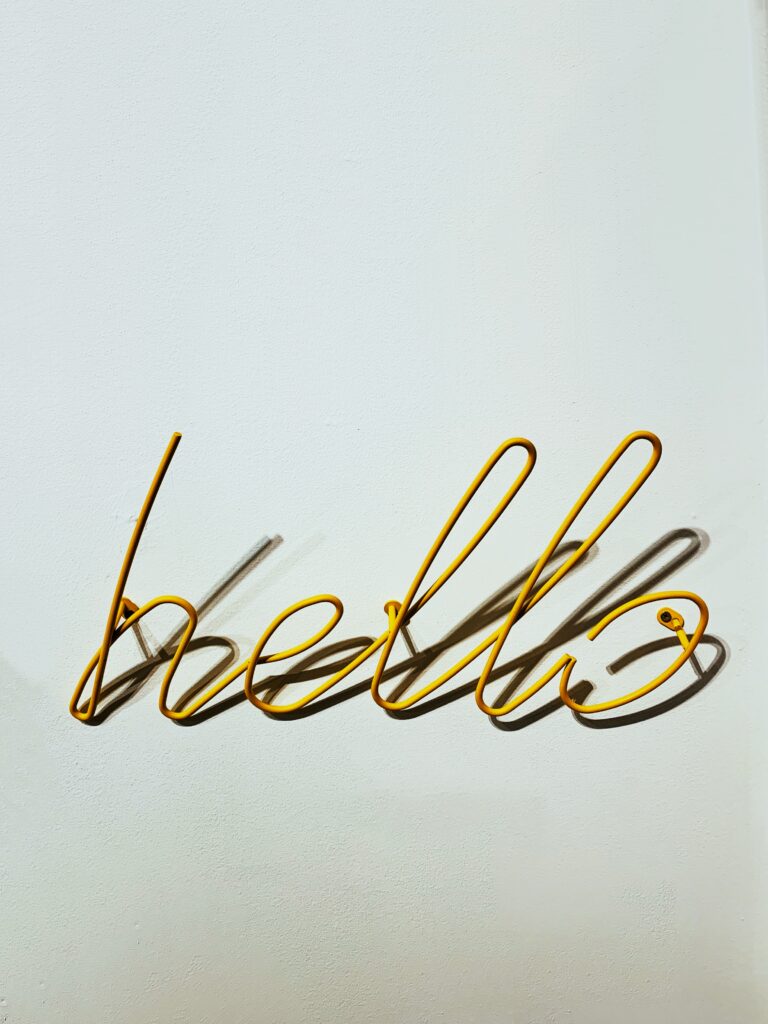
2025年4月改正分はこちら
雇用保険とは
社会保険(公的保険)の中に、医療保険、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、雇用保険、年金保険があります。
今回はその中の雇用保険についてです。
雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。
加入要件:雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 31日以上の雇用見込みがあること
保険料:給与額または賞与額×保険料率
保険料率で、給料より月数百円程度ひかれています。保険料率について(厚生労働省HP)
受給資格:離職日以前2年間に雇用保険の一般保険者であった期間が、通算して1年以上(倒産・解雇のときは離職日以前1年間に6か月以上)あること。
給付:基本手当(失業者の求職活動中に支給)・就職促進給付(基本手当支給期間に再就職した時に支給)・教育訓練給付(厚生労働大臣指定の教育訓練を受ける時に支給)・雇用継続給付(高齢者や介護休業者に支給)・育児休業給付(育児休業取得者に支給)
基本手当
基本手当は、失業したときに支給されます。
申請:公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをすることが必要
受給期間:離職した日の翌日から1年間(病気、出産・育児、介護等で30日以上継続勤務できなくなった場合は最長3年延長でき、合計4年間が限度になる。)※受給日数が増えるわけではない。
給付日数:被保険者期間や年齢などによって異なる。

特定受給資格者及び特定理由離職者について(ハローワークインターネットサービス)
給付金額: 基本手当日額(賃金日額×45~80%)×日数
※賃金日額=離職日の直前6か月に毎月支払われた賃金(賞与等は除く)の合計÷180日
また賃金日額には上限と下限が決まっており下記をご参照ください。
基本手当日額について(厚生労働省ハローワーク)
待機期間と給付制限期間 給付は、退職後7日間の待期期間の経過後に支給される。 自己都合や重責解雇の場合は、退職後7日間の待期期間+最長2か月間の給付制限期間の経過後に支給される。 要するに、会社都合等で退職1か月後、自己都合等で退職3か月後くらいに支給が開始される。

就職促進給付
就職促進給付は、失業者が早期の就職をしたときに支給されます。
【再就職手当】…雇用保険の基本手当支給期間に、支給日数を3分の1以上残して、職業に就き、一定条件を満たした場合に支給されます。
支給金額
支給残日が所定給付日数の3分の2以上:所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
支給残日が所定給付日数の3分の1以上:所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額
※基本手当日額の上限は、6,290円(60歳以上65歳未満は5,085円)※毎年8月1日以降に変更可能性あり
【職業促進定着手当】…再就職後の賃金が離職前の賃金より低下した場合に支給されます。
支給金額
(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数
※上限額:基本手当日額(上限6,290円(60歳以上65歳未満は5,085円))×基本手当の支給残日数に相当する日数
×40%(再就職手当の給付率が70%の場合は30%)
教育訓練給付
教育訓練給付は、主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されます。
離職してから1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由により適用対象期間の延長を行った場合は最大20年以内)で、雇用保険の加入期間が1年以上(専門実践教育訓練を受講する場合は2年以上)ある場合受けられます。
※給付を受けたことがある場合は、前回の支給日から今回の受講開始日までに3年以上経過していないと受けれません。
【専門実践教育訓練】
支給金額:最大で受講費の50%(年間上限額40万円)
また資格取得後に就職した場合は20%(年間上限16万円)追加
※令和6年10月以降受講の場合、賃金5%以上上昇したら10%(上限額8万円)追加支給
支給期間:最長3年間
対象講座:ITSSレベル3相当以上のIT関係資格取得、第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)、専門職大学院の課程、職業実践専門課程(文部科学大臣認定)、介護福祉士、看護師・准看護師、美容師、社会福祉士、歯科衛生士、保育士、調理師、精神保健福祉士、はり師 など
【特定一般教育訓練】
支給金額:受講費用の40%(上限額20万円)
※令和6年10月以降受講の場合、10%(上限額5万円)追加支給
支給期間:最長1年間
対象講座:・ITSSレベル2相当以上の情報通信資格の取得、介護支援専門員実務研修、介護職員初任者研修、特定行為研修、大型自動車第一種・第二種免許 など
【一般教育訓練】
支給金額:受講費用の20%(上限額10万円)
支給期間:最長1年間
対象講座:修士・博士の学位などの取得を目標とする課程、輸送・機械運転関係(大型自動車、建設機械運転等)、介護福祉士実務者養成研修、介護職員初任者研修、税理士、社会保険労務士、Webクリエイター、CAD利用技術者試験、TOEIC、簿記検定、宅地建物取引士 など
【専門実践教育訓練】
支給金額:最大で受講費の50%(年間上限額40万円)
資格取得後に就職した場合は20%(年間上限16万円)追加
※令和6年10月以降受講の場合、賃金5%以上上昇したら10%(上限額8万円)追加支給
支給期間:最長3年間
対象講座:ITSSレベル3相当以上のIT関係資格取得、第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定)、専門職大学院の課程、職業実践専門課程(文部科学大臣認定)、介護福祉士、看護師・准看護師、美容師、社会福祉士、歯科衛生士、保育士、調理師、精神保健福祉士、はり師 など
【特定一般教育訓練】
支給金額:受講費用の40%(上限額20万円)
※令和6年10月以降受講の場合、10%(上限額5万円)追加支給
支給期間:最長1年間
対象講座:ITSSレベル2相当以上の情報通信資格の取得、介護支援専門員実務研修、介護職員初任者研修、特定行為研修、大型自動車第一種・第二種免許 など
雇用継続給付
雇用継続給付は、60~65歳未満の一般被保険者が、60歳以降の賃金が規定の基準まで低下した時や、家族を介護するために休業した時に支給されます。
【高年齢雇用継続給付】
高年齢雇用継続基本給付金
60~65歳未満で、継続雇用で賃金が下がった時、条件を満たした場合に支給。
受給資格:下記のすべてに当てはまっている方。
①60~65歳未満の被保険者
②被保険者期間が通算5年以上ある。
③60歳以後の賃金月額が60歳時点の75%未満であること。
支給額:支給対象月に支払われた賃金×15%相当額
高年齢再就職給付金
60~65歳未満で、再就職で賃金が下がった時、条件を満たした場合に支給。
受給資格:下記のすべてに当てはまっている方。
①60~65歳までに再就職して被保険者となった。
②被保険者期間が通算5年以上ある。
③再就職の賃金月額が、基本手当の基準となった賃金日額×30の金額の75%未満であること。
④再就職の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
支給額:支給残日数×基本手当日額×60%(残数が3分の2以上)または70%(残数が3分の1以上)
支給額は、各支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金の低下率の応じて算定されるが、「みなし賃金」や「支給限度額」などにより支給額が減額されたり、支給がなされないことがある。
【介護休業給付】
受給資格:負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を、介護するための休業であること。
被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、実際に取得した休業であること。
対象者:配偶者・父母・子・配偶者の父母・同居の祖父母、兄弟姉妹、孫。
支給期間:介護対象家族1人につき93日を限度に、3回まで分割して取得可能。
支給額:休業開始時賃金日額×67%
育児休業給付
育児休業給付は、子の出生日後に育児休業した時に支給されます。条件を満たしていれば、母と父どちらも取得可能です。
【出生時育児休業給付金】
子の出生日後に、養育するための産後育休を取得した被保険者に支給されます。
受給資格:下記すべてに当てはまっている方。
①子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内※1で、事業主が取得を認めた休業であること。
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日(または80時間)以上ある月が12か月以上あること。
③休業期間中の就業日数が最大10日(または80時間)以下であること。
④出生時育児休業期間を対象として、休業開始時賃金日額×休業期間の日数の8割以上の賃金が支払われていないこと。
⑤子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約期間が満了しないこと。
※1…「出生日または出産予定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内に4週間(28日)の範囲で取得されたもの。
支給期間:子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内で4週間(28日)。2回まで分割可能。
支給額:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)× 67%
※休業開始時賃金日額には上限額と下限額があります。
※育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合は、減額されます。
【育児休業給付金】
期間内に、育児休業を取得した被保険者に支給されます。
受給資格:下記すべてに当てはまっている方。
①1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること。(2回まで分割取得可)
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日(または80時間)以上ある月が12か月以上あること。
③育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間の就業日数が最大10日(または80時間)以下であること。
④育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始時賃金日額×休業期間の日数の8割以上の賃金が支払われていないこと。
⑤養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、労働契約期間が満了しないこと。
支給期間:出産8週間後から1歳未満(条件により最大2歳未満)で取得した期間。2回まで分割可能。
支給額:休業開始時賃金日額×支給日数(原則30日)×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
対象月数まで請求できます。
※休業開始時賃金日額には上限額と下限額があります。
※育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合は、減額されます。
●パパママ育休プラス制度(父母がともに育児休業を取得する)を申請すると、1歳2か月未満まで期間延長できる。 ●支給対象期間延長(預けられる保育所がない時など)に該当する場合は申請することで、1歳6か月または2歳未満まで期間延長でき、3回目以降の分割も可能。 ●また延長事由に該当していれば、1歳以降の育児休業も夫婦1回ずつ延長交替できる。 1歳から1歳6か月までの期間と、1歳6か月から2歳までの期間で、それぞれで配偶者が育児休業をしていれば、延長交替として育児休業の取得が認められる。 その際、配偶者の休業期間と接していないと取得は認められない。継続していれば、父母同時に取得することも可能。

まとめ
今回は、社会保険の中の雇用保険について解説しました。
・失業したときに、基本手当
・失業者が早期の就職をしたときに、就職促進給付
・主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了したときに、受講費用の一部が支給される、教育訓練給付
・60~65歳未満の被保険者が60歳以降の賃金が低下した時や、家族を介護するために休業したときに、雇用継続給付
・子の出生日後に育児休業した時ときに、育児休業給付
が受給できます。失業したときに保障があるのはありがたい制度ですよね。この制度を知っているだけでも、失業を恐れずに前に進める気がします。
社会保険(公的保険)の中には雇用保険のほかに、医療保険、介護保険、労働者災害補償保険(労災保険)、年金保険があります。ご興味がある方は、クリックしてご覧ください。
↓転職先探したい方はこちらから↓

2025年4月改正分はこちら






コメント